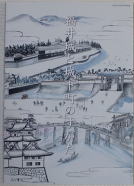徳川家康の次男結城秀康は、慶長5年(1600)に初代福井藩主となり、翌慶長6年(1601)に越前へ入国しました。同年から6年掛かりで、かつての北の庄城の大修築を行い、慶長11年(1606)に福井城が完成しました。大修築の福井城は、最大幅が100mにも及ぶ百間堀をはじめ、四重、五重の堀に囲まれた広大な城で高さが約30m、四層五重の天守がそびえていました。
しかし、寛文9年(1669)に発生した大火により、天守は多くの櫓や城門とともに焼けてしまい、その後天守が再建されることはありませんでした。代わりに、それまで二重櫓だった巽櫓および坤櫓を三重櫓として再建し、天守の代用としました。幕末まで福井藩越前松平家の居城であった福井城でしたが、明治以降に櫓や塀などが順次取り壊され、外堀も埋め立てられました。
※お城のパンフレット(福井城山里口御門)より引用
|
| |
| 概要 |
平城 |
| 別名 |
北の庄城 |
| 築年/廃年 |
慶長6年(1601)/明治以降 |
| 築城主 |
結城秀康 |
| 歴代城主 |
結城(松平)秀康→松平忠直→忠昌→松平氏 |
| 所在地 |
福井県福井市大手 |
| 最寄り駅 |
JR北陸本線 福井駅 徒歩5分 |
| 最寄りIC |
北陸自動車道 福井IC 国道158号線→国道8号線→県道114号線経由 |
| 駐車場 |
有(有料) 福井駅西地下駐車場(福井駅の西側)
福井市大手駐車場(中央公園南)
駐車場はこちらをご覧ください |
| 休館日 |
土日祝、年末年始(県庁の休館日 お城は随時見学可能) |
| スタンプ設置場所 |
福井県庁舎一階受付
福井県庁は休みでしたが、職員通用口でインターホン押して声をかけた らスタンプを押させてくれました |
| ウェブサイト |
ふくいドットコム |
休日に訪問したため県庁が休みでしたが、職員通用口のインターホンを押して声をかけたら
快く中に入れていただきスタンプを出していただきました。
他に職員の方や業者の方の通行も多かったので守衛の方も大忙しでした。
城内では天守台に昔、福井の大震災があった時に崩れた石垣がそのままの状態で残っていました。
見どころ
◆天守台
◆山里口御門
◆御廊下橋
◆石垣
◆福の井
等が見どころとなります。
観光スポット
| 福井市立郷土歴史博物館 |
福井市立郷土歴史博物館は、あいつぐ戦災と震災から復興した福井市のシンボルとして、昭和28年足羽山に開館しました。以来、郷土福井に関する資料の収集に努め、福井市春嶽公記念文庫をはじめとする福井藩、越前松平家に関する資料が充実しています。
※福井市立郷土歴史博物館HPより引用 |
| 北の庄城址資料館 |
柴田勝家公が行った偉業の紹介や北庄城に関する遺物や資料を展示しています。
※まなびぃネットふくいHPより引用 |
| 福井県立歴史博物館 |
福井のモノづくりやモノをテーマにした歴史ゾーンや、トピックゾーンによる展示のほか、博物館の収蔵庫をイメージした展示を行い、資料の歴史や調査などの様子を見ることができるオープン収蔵庫や、映像資料などが見られる情報ライブラリーを備えています。
※GOOBA/グーバHPより引用 |
イベント
毎年7月に福井城址お堀の灯りが行われ、空襲や震災を偲び、福井城址や中央公園などを約6,800個のキャンドルなどの灯りでライトアップします。
ステージでは和太鼓や二胡の演奏などが行われ、食の広場ではケータリングカーや屋台が並びます。
書籍
 福井市立郷土歴史博物館で書籍を販売しています 福井市立郷土歴史博物館で書籍を販売しています
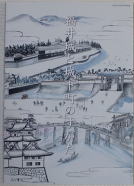 |
<書籍の内容について>
第一章 失われた城下町」の景観をみる
第二章 クローズアップ「福井城と武家屋敷」
第三章 考古学が語る城下町のすがた
第四章 城下町の賑わいをみる |
|
|